残業代を含む営業手当の定額払いは認められますか?
 当社は、営業職の従業員に対して、残業代を含むものとして営業手当を支給しています。このような残業代の定額払いは認められますか?
当社は、営業職の従業員に対して、残業代を含むものとして営業手当を支給しています。このような残業代の定額払いは認められますか?

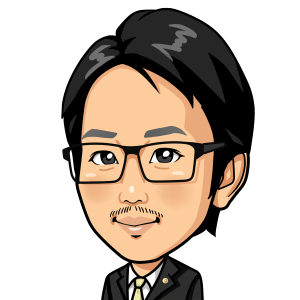 残業代の定額払いが認められるには、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金相当部分とが明確に区分されていることなどの厳格な要件を満たす必要があります。
残業代の定額払いが認められるには、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金相当部分とが明確に区分されていることなどの厳格な要件を満たす必要があります。
問題の背景
 労働基準法は、時間外労働等(休日労働や深夜労働を含む。)について、所定の割増率による割増賃金を支払うことを使用者に義務付けています(労基法37条)。
労働基準法は、時間外労働等(休日労働や深夜労働を含む。)について、所定の割増率による割増賃金を支払うことを使用者に義務付けています(労基法37条)。
しかし、毎月、従業員一人ひとりの割増賃金を計算するのは煩雑です。
そこで、割増賃金を支払う代わりに、定額の手当を時間外労働の対価として支払ったり(定額手当制)、基本給に割増賃金を組み込んで支払ったり(定額給制)するケースがあります(定額手当制と定額給制を合わせて固定残業代制といいます。)。
このような固定残業代制は、給与計算事務の負担軽減という観点からは合理性があるといえます。また、固定残業代の金額が法所定の割増賃金よりも多額であれば、労働者にとっても有益といえます。
しかし、固定残業代の金額が法所定の割増賃金よりも少額の場合はいわゆるサービス残業問題となり、労働者に大きな負担となってしまいます。
実際に、この固定残業代制については、労働紛争となることが多く、裁判等に発展することも珍しくありません。そこで、このような固定残業代制が認められるのか、認められる場合その要件をどう解するかが問題となります。
裁判例や学説の見解
固定残業代制自体の有効性
労働基準法37条は、時間外労働等について、所定の割増率による計算を規定します。
しかし、同法は、法所定の計算による一定額以上の割増賃金を支払うことを求めているのであって、これに違反しない限り、同法による計算をする必要はないと考えられています(昭和24年1月28日基収第3947号)。
 例えば、割増賃金の計算の基礎に算入すべき賃金を除外していても、割増率を高くしているために実際に支払われる割増賃金の額が労働基準法所定の計算による割増賃金額以上となる場合、違法とはなりません。
例えば、割増賃金の計算の基礎に算入すべき賃金を除外していても、割増率を高くしているために実際に支払われる割増賃金の額が労働基準法所定の計算による割増賃金額以上となる場合、違法とはなりません。
ただし、「割増賃金として法所定の額が支払われているか否かを判定できるように、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金相当部分とを区別できるようにすること」が必要であると考えられています(菅野498頁、東和システム事件・東京高判平成21年12月25日労判998号5頁など)。
定額手当制
例えば、労働者に対して、残業代を含むものとして、営業手当(前掲東和システム事件)、セールス手当(名鉄運輸事件・名古屋地判平3年9月6日)、運行手当(関西ソニー販売事件・大阪地判昭和63年10月26日)などの手当を支給している類型です。
会社としては、従業員に対して、残業代を含む趣旨で支給している手当であっても、従業員から「残業代をもらっていない。」として未払賃金を請求されるケースが多々あります。
この場合、仮に、会社の主張が認められなければ、割増賃金算定の基礎となる賃金に当該手当が加算された上で時間外等の割増賃金を計算する必要が生じるため、会社が支払う未払賃金額は莫大な金額となる可能性があります。
【参考判例】前掲東和システム事件
 この事案は、課長代理職にある者に対して支給されていた「特励手当」が割増賃金の算定基礎に含まれるか否かが争点の1つとなったものです。
この事案は、課長代理職にある者に対して支給されていた「特励手当」が割増賃金の算定基礎に含まれるか否かが争点の1つとなったものです。
1審(東京地裁)では、特励手当は残業代を含まないと判断し、原告ら3名の未払賃金請求を認めました。
これに会社側が控訴したところ、東京高裁は、1審を覆し、特励手当は残業代を含むとして、同手当を割増賃金算定の基礎に含めませんでした。
以下、争点に関する判旨の抜粋部分です。
①特励手当は、給与規程23条の「管理職務者(課長職及び同相当職以上のもの)及びこれに準ずる者(課長代理職)は、特励手当として基本給の30%を支給する。」との規定に基づいて支給されているものであり、控訴人において所定時間外労働(残業)が恒常的に予定されるとしている「課長代理」以上の職位にある者に支払われるものであること、
②特励手当は、基本給の30%に相当する金額であって、定額ではなく、同じ「課長代理」の職にある者であっても基本給が異なれば特励手当の額も異なるのであり、特励手当が「課長代理」の職そのもののみに関係しているとはいい難いこと、
③特励手当の前身であると認められる精励手当について、旧職員給与規程(〈証拠省略〉)の22条1項は、「管理職務者および業務上勤務時間不定期又は監督者が勤務時間を認定困難な部署の職員が職務に精励した場合精励手当を次の通り支給する。」として、「男子職員基準内給与の30%(家族手当を除く)」、「女子職員〃15%(家族手当を除く)」とし、同規程23条3項で、明文をもって、「超過勤務手当は前条の精励手当受給者には支給しない。」と規定しており、超過勤務手当の支給と精励手当の支給とは重複しないもの(択一的であること)としていたこと、
④控訴人の認識においても、特励手当は、一般職から管理職に昇任したことに伴い、それまでの超過勤務手当に代わるものとして基本給の30%に相当する額を支給するものであり、超過勤務手当に代替してこれを填補する趣旨のものであると認識していること、
⑤控訴人において、これまで、特励手当と超過勤務手当とを重複して支給したことはなく、特励手当は職制上の「課長代理」以上の職位にある管理職に支給し、超過勤務手当は職制上の「課長代理」より下位の職位にある一般職に支給してきたこと、
⑥給与規程の体裁上も、給与はまず基準内給与と基準外給与に分けられ、基準内給与として基本給(年齢給及び職能給)、職務手当、技術手当、住宅手当及び家族手当が規定され、基準外給与として超過勤務手当、特励手当、特務手当、通勤手当、公傷病手当、障害手当及び留守家族手当が規定されており(2条)、超過勤務手当も特励手当もともに基準外給与として規定されていて、まず22条で超過勤務手当について定められた後、23条で特励手当について定められていること、
⑦もし「課長代理」の職にある者に超過勤務手当を支給するとすると、一般職のときには超過勤務手当の支給しか受けなかったのに、「課長代理」に昇任したことによって超過勤務手当のほかに特励手当の支給も受けることになり、さらに、「課長代理」職より上位の「課長」職に昇任すると逆に特励手当の支給しか受けられなくなって不利益となるのであり、このような給与規程の解釈は不合理といわざるを得ないこと、
⑧被控訴人らの基本給は、平成17年2月から平成20年7月まで(ただし、被控訴人X2については同年10月まで)の間において、被控訴人X1が47万0900円ないし47万1900円、被控訴人X2が46万7600円ないし47万1900円、被控訴人X3が46万2800円ないし47万1900円であって、基本給がことさらに低額に抑えられているとはいい難いこと、以上の諸点を考慮すると、特励手当は超過勤務手当の代替又は補填の趣旨を持っており、特励手当の支給と超過勤務手当の支給とは重複しないもの(択一的なもの)と解するのが相当であり、特励手当は「管理職務者及びこれに準ずる者」の所定時間外労働(残業)について支給されるものであり、超過勤務手当は「管理職務者及びこれに準ずる者」以外の者すなわち一般職の所定時間外労働(残業)について支給されるものであると解するのが相当である。 そうとすれば、特励手当を超過勤務手当算定の基礎となる賃金に含ましめるべきではなく、これから除外するのが相当である。」
定額給制
定額給制は、基本給の中に残業代を組み込んで支給するものです。
このタイプの固定残業代制は、前記の定額手当制の場合よりも、通常の労働時間の賃金部分と割増賃金相当部分との区別が曖昧で、割増賃金として法所定の額以上が支払われているか否かの判定が困難な場合が多くあります。
実際に問題となった裁判例をご紹介します。
【参考判例】小里機材事件(最一判昭和63年7月14日労判523号6頁)
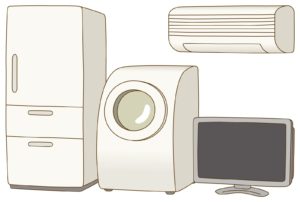 この裁判例は、固定残業代制が最高裁まで争われた事案としてリーディングケースとなっています。
この裁判例は、固定残業代制が最高裁まで争われた事案としてリーディングケースとなっています。
この事案では、原告ら5名の未払い割増賃金等の請求に対し、会社側は、雇用の際、月15時間の時間外労働に対する割増賃金を本来の基本給に加算して基本給とする旨合意したため、原告が会社側に請求できるのは、月15時間を超える時間外労働に対する割増賃金についてのみであるなどの反論がなされた事案です。
裁判所(1審・東京地判昭和62年1月30日)は、「仮に、月一五時間の時間外労働に対する割増賃金を基本給に含める旨の合意がされたとしても、その基本給のうち割増賃金に当たる部分が明確に区分されて合意がされ、かつ労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されている場合にのみ、その予定割増賃金分を当該月の割増賃金の一部又は全部とすることができるものと解すべき」とし、そのような合意がされた旨の主張立証がないと認定し、会社側の反論を採用しませんでした。
なお、2審(東京高判昭和62年11月30日)は、この1新判決をそのまま引用して控訴棄却とし、最高裁も原判決を維持しました。
この裁判例を素直に読むと、固定残業代制が有効となる要件としては、
①基本給のうち割増賃金に当たる部分が明確に区分されて合意がされていること(以下、「明確区分性の要件」といいます。)、
②労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことが合意されていること(以下、「超過精算の合意」といいます。)、
という2つの要件を満たす場合に限り、固定残業代制が有効となるとも考えられます。
しかし、この裁判例に対しては、①の明確区分性の要件は必要だとしても、②の超過精算の合意は、労働基準法上当然のことなので、わざわざ独立の要件と考えるべきではないとする批判がなされました。
また、最高裁判例といっても、下級審を維持したにすぎず、最高裁が②の超過精算の合意が必要であると明示したものではありませんでした。
そのため、この判決以降も、固定残業代制が争点となった他の事案において、①の明確区分性の要件のみで判断した事案が多く見られました。
しかし、近年、②の超過精算の合意の要件について参考となる裁判例が出ているので紹介します。
【参考判例】テックジャパン事件(最一判平成24年3月8日労判1060号5頁)
 この事案も固定残業代制が争点となった事案です。
この事案も固定残業代制が争点となった事案です。
判決の中で、櫻井裁判官の補足意見が注目されました。
補足意見は、以下のとおりです(抜粋)。
「本件に関し、労働基準法等の趣旨を踏まえ若干指摘しておきたい点があるので、補足意見を付しておきたい。(中略)そのような法の規定を踏まえ、法廷意見が引用する最高裁平成6年6月13日判決は、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別し得ることが必要である旨を判示したものである。本件の場合、その判別ができないことは法廷意見で述べるとおりであり、月額41万円の基本給が支払われることにより時間外手当の額が支払われているとはいえないといわざるを得ない。便宜的に毎月の給与の中にあらかじめ一定時間(例えば10時間分)の残業手当が算入されているものとして給与が支払われている事例もみられるが、その場合は、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならないと同時に支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないであろう。さらには10時間を超えて残業が行われた場合には当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべきと思われる。本件の場合、そのようなあらかじめの合意も支給実態も認められない。」
この補足意見は、明確区分性の要件だけではなく、超過精算の合意の要件が必要であるとの見解に立っているものと考えられます。
また、この判決以降、下級審でも超過精算の合意が必要であるという前提に立った判決が出ています(イーライフ事件・東京地裁平成25年2月28日)
このような状況を踏まえると、会社としては、訴訟リスクを回避するため、超過精算の合意を締結しておくことが無難といえるでしょう。
実務上の留意点
 固定残業代をめぐる紛争は、労働者側の請求が認められた場合、会社への影響が大きい事案です。会社側が裁判で敗訴すると、すでに支払っていると認識していた残業代が支払われていなかったこととなりますし、割増賃金を算出する基礎賃金の額も大きくなるため、未払賃金額が高額化する傾向となります。
固定残業代をめぐる紛争は、労働者側の請求が認められた場合、会社への影響が大きい事案です。会社側が裁判で敗訴すると、すでに支払っていると認識していた残業代が支払われていなかったこととなりますし、割増賃金を算出する基礎賃金の額も大きくなるため、未払賃金額が高額化する傾向となります。
また、複数名から未払賃金を請求されると、支払い原資がない企業の場合、倒産のリスクもあります。そのため、未然防止の必要性が大きいといえます。
そのために、①明確区分性の要件と②超過精算の合意の要件を踏まえた防衛策をとっておくべきです。
固定残業代制の規定例
①定額手当制の場合
第◯条(営業手当)
1.営業職の従業員に対し、月額○○円の営業手当を支給する。
2.前項の営業手当は、その全額を1か月○○時間の時間外勤務手当として支給する。
3.前項に定める営業手当を支給された従業員について、第1項に定める営業手当の額を超えて、時間外割増賃金が発生した場合には、別途、その差額を時間外勤務手当として支給する。
②定額給制の場合
第◯条(定額給制)
1.基本給のうち、○円は、 1か月○時間の時間外労働に対する時間外勤務手当とする。
2.前項に定める時間外勤務手当の額を超えて、時間外勤務手当が発生した場合には、別途、その差額を支給する。
上記はあくまで一例です。会社の状況によって、最適な規定の仕方は異なりますので、労働問題に詳しい専門家にご相談ください。
 当事務所の労働弁護士は、使用者側専門であり、企業を護る人事戦略をご提案しています。
当事務所の労働弁護士は、使用者側専門であり、企業を護る人事戦略をご提案しています。
まずはお気軽にご相談ください。









