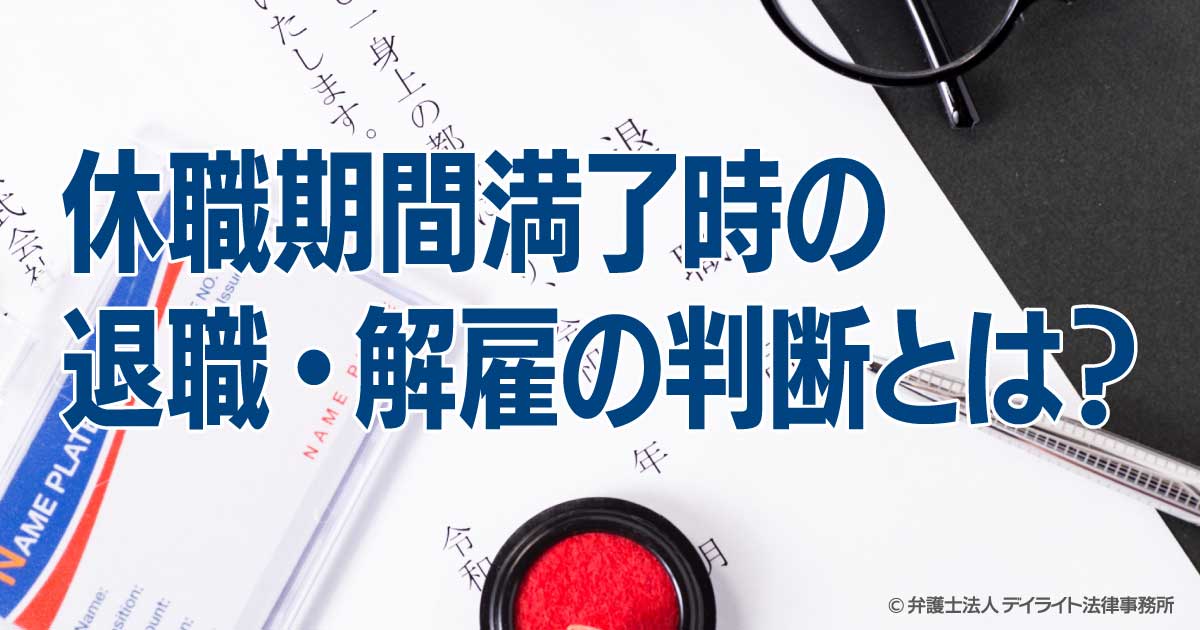不当解雇とは|正当な解雇との違いや対処法を弁護士が詳しく解説
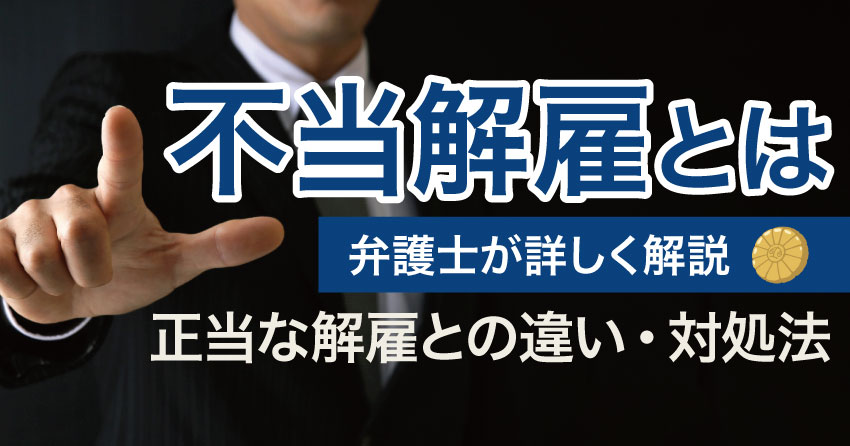
目次
不当解雇とは
不当解雇とは、企業や経営者の行う解雇が法的に正当とは認められないものをいいます。
「不当解雇」という言葉そのものが法律で規定されているわけではありません。
そもそも解雇とは、会社側が従業員に対して、一方的に雇用契約の解消を通知することです。
会社側が一方的に従業員に通知することができるわけなので、気に入らない従業員がいるからといって、会社がいつでも、自由に解雇を通知することができるかというと決してそんなことはありません。
過去の歴史に少し触れると、産業革命で急速に近代化が進みましたが、その際、どうしても人を雇う側(使用者)の力が強く、そこで働く人(労働者)の地位は非常に弱いものでした。
当事者間の契約については、「契約自由の原則」というルールがあります。
このルールは、どのような相手とどのような内容で契約をするかは自由というものです。
ただし、先ほど触れた歴史的な経験も踏まえ、人を雇う雇用契約においては、どうしても雇う側の立場が強くなるという点を修正しなければならないと考えられています。
その結果、雇用契約に関しては、労働基準法や労働契約法といった様々な法律でルールを定めています。
企業が解雇できる条件

このように、企業が解雇するのはいつでも、自由にできるわけではありません。
解雇を有効に行うためには、一定の条件があるのです。
まず、法律で解雇ができない場合として規定されているものがあります。
上記に該当しない解雇でも、形式面、内容面で一定のルールが定められています。
法律で規定された解雇ができない場合
法律で解雇ができない場合として規定されているものもあります。
以下の通りです。
産前産後期間中の解雇
労働基準法19条は、女性が産前産後休業をしている期間とその後30日間は解雇してはならないと定めています。
産前産後休業とは、出産予定前6週間(双子以上の場合は14週間)で本人が請求した場合と産後8週間の期間の休業のことをいいます。
業務災害の解雇
労働基準法19条は、産前産後休業とあわせて、従業員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間は解雇してはならないと定めています。
労災事故によるけがで入院している場合が例として挙げられます。
なお、通勤災害は労災保険の対象ではありますが、ここでいう「業務上負傷し」に該当しないため、通勤災害による休業中に解雇をすることは、この規定には当たりません。
差別的解雇
労働基準法3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、差別的取扱いをしてはならないと定めています。
この規定から、国籍、信条、社会的な身分を理由として解雇をすることはできません。
同じく、労働組合法7条で、従業員が労働組合に加入したこと、特定の労働組合で活動していることを理由として解雇をすることはできません。
性別を理由とした解雇
国籍、信条又は社会的身分を理由とした解雇とは別に、男女雇用機会均等法という法律で、性別を理由とする解雇も禁止されています。
具体的には、「事業主は、労働者の募集及び採用について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。」と定めていて(6条)、その一つに「退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新」が挙げられています(4号)。
このように、様々な法律で解雇がそもそもできない場合が複数定められています。
したがって、これまでに説明した解雇はいずれも不当解雇になります。
形式面
 30日前の予告期間をおくか、30日分の平均賃金を支払う
30日前の予告期間をおくか、30日分の平均賃金を支払う解雇は従業員の生活の基盤である給与、職を失うことを意味します。
そのため、企業側には従業員に1か月程度の猶予を与えることが要求されています。
それが労働基準法20条です。
猶予を与える方法は基本的に2つで、
- 少なくとも30日前に解雇を伝える
- 30日分の平均賃金を支払う
のいずれかになります。
具体例 6月1日に解雇をしたい場合
基本的な解雇の方法は以下の通りです。
- 30日より前の5月1日までに解雇の通知をする
- 6月1日に解雇を通知し、その代わりに30日分の平均賃金を支払う
※解雇予告と平均賃金の支払いの併用により30日の要件を満たすことは可能です。したがって、以下の方法で解雇を行うことでも形式面はクリアすることになります。
- 5月15日に解雇を通知し、30日に満たない14日分の平均賃金を支払う
内容面
法律で規定された解雇できない場合に該当せず、形式面の手続を守っていたとしても、解雇が有効になるわけではありません。
この部分が内容面に関するものです。
当初、この内容面に関する部分は裁判所の判例で確立されていきました。
これを「解雇権濫用法理」といいます。
漢字のとおり、企業側に認められている解雇権の行使が行き過ぎていないか、その権利を濫用していないかをチェックするのが、この考え方になります。
こうした法理が確立した理由としては、最初に説明した、会社側が自由に解雇をすることができやすい反面、解雇により従業員が受ける影響が大きくなるという解雇の性質によります。
そして、この解雇権濫用法理が法律で明記されるようになりました。
具体的には、労働契約法16条です。
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この記載から、内容面として、解雇には、
 客観的、合理的な理由
客観的、合理的な理由 社会通念条の相当性
社会通念条の相当性という2つが求められていることがわかります。
そして、この2つの要件が満たされていないと判断されると、会社側の解雇は解雇権の濫用として、無効になります。
こうした無効な解雇というのが、一般的に使用される不当解雇と同義と考えられます。
不当解雇になった場合の効果
会社側が行った解雇が不当解雇となった場合、先ほどご紹介した労働契約法16条からも、解雇が無効になります。
解雇が無効ということは、会社が行った解雇はなかったことになります。
具体例で説明します。
具体例 会社側が行った解雇が不当解雇となった場合
2022年6月1日に会社がある従業員Aさんを解雇したものの、その後2024年5月31日に解雇が不当解雇と判断されたとします。
この場合、2022年6月1日に会社が行った解雇は無効となり、解雇がなかったことになります。
そうすると、法律的には、Aさんは2024年5月31日時点でも会社に在籍しているということになります。
したがって、Aさんが会社への復帰を望んでいる場合、会社はAさんを復職させなければならないというのが原則です。
仮に働かせないとしても、不当解雇だったことでAさんは会社に在籍しているので、会社は毎月給与をAさんに支払い続けなければなりません。
また、過去の給料についてですが、不当解雇と判断されるまでの間の2年間、Aさんは会社で仕事をすることはできていません。
ノーワークノーペイの原則からすれば、働いていない以上給料は発生しないと考えられます。
しかしながら、Aさんが働くことができなかったのは会社による不当解雇が原因ということになります。
したがって、不当解雇と判断された場合、判断されるまでの間の給料も会社がAさんに支払わなければなりません。
このように会社の行った解雇が不当解雇となってしまうと、それまでの給与の支払いと復職について会社が対応しなければならなくなってしまいます。
不当解雇に該当するケース

不当解雇になるケースというのは、上述の「企業が解雇できる条件」のところで解説した条件を満たしていない解雇ということになります。
内容面に関しての、客観的・合理的な理由、社会通念上の相当性がどのような場合に認められているかについては、解雇の種類によっても変わってきます。
整理解雇で不当解雇に該当するケース
 リストラという形式をとってはいるものの、特定の人を狙い撃ちしたような解雇や売上低迷により、リストラの必要性はあっても、配置転換などの措置を取れる規模の会社でそうした措置をとることなくいきなり大量リストラをしたといったケースでは不当解雇になる可能性が高いでしょう。
リストラという形式をとってはいるものの、特定の人を狙い撃ちしたような解雇や売上低迷により、リストラの必要性はあっても、配置転換などの措置を取れる規模の会社でそうした措置をとることなくいきなり大量リストラをしたといったケースでは不当解雇になる可能性が高いでしょう。整理解雇については、過去の裁判例において、4つの点を考慮して不当解雇になるかどうかを決定するとされています。
- 人員削減の必要性 経営不振や不況を理由としてそもそも人員削減がやむを得ない措置かどうか
- 削減のための解雇の必要性 配置転換や出向などの手段で対応できないのかどうか
- 人選の合理性 整理解雇する人員をどのように選んでいるか、その選択に問題はないか
- 手続の妥当性 労働者と整理解雇に至るまでにどのような話合いがなされていたか
懲戒解雇で不当解雇に該当するケース
 会社の上司の命令に反いたといった理由だけで懲戒解雇をした場合には、職場秩序を乱す行為ということはいえたとしても、それで懲戒解雇というのは重すぎるとして不当解雇になる可能性があります。
会社の上司の命令に反いたといった理由だけで懲戒解雇をした場合には、職場秩序を乱す行為ということはいえたとしても、それで懲戒解雇というのは重すぎるとして不当解雇になる可能性があります。懲戒解雇については、そもそも就業規則に懲戒についての規定が定められているかどうか、解雇の理由となっている事実が懲戒解雇という懲戒処分の中でも一番重たい理由として相当かどうかという点が考慮されて、不当解雇かどうかを判断することになります。
普通解雇で不当解雇に該当するケース
 数回程度の遅刻を理由に解雇したり、1、2件のクレームから直ちに能力不足として解雇したりすることは不当解雇に当たる可能性が高いでしょう。
数回程度の遅刻を理由に解雇したり、1、2件のクレームから直ちに能力不足として解雇したりすることは不当解雇に当たる可能性が高いでしょう。普通解雇については、整理解雇や懲戒解雇と異なり、具体的な解雇理由ごとに客観的・合理的な理由、社会通念上の相当性が認められるかどうかをチェックすることになりますが、解雇は従業員に対する与える影響が大きいので、日本の裁判実務では、比較的要件が厳しく判断されています。
不当解雇にならないケース
企業が行った解雇が不当解雇にならないケースというのは、解雇できない条件に当たらず、形式面の要件も満たし、内容面の要件、すなわち、客観的・合理的な理由、社会通念上の相当性をともに満たしている解雇ということになります。
ケースバイケースなので、明確にできない部分もありますが、解雇が正当と認められるケースとして例を挙げると以下のようなものが考えられます。
※あくまで一例です。
赤字が複数年にわたって継続しており、希望退職もすでに募った上でさらなる人員削減のために行った解雇懲戒解雇
複数の顧客からの預かり金を自己の借金返済のために使い込んだことが判明したことで行った解雇普通解雇
遅刻や無断欠勤を何度も注意しているにもかかわらず、1、2年繰り返す従業員に対し、改善の見込みがないとして行った解雇
不当解雇で企業が受ける罰則
不当解雇と判断されるとすべての解雇で罰則が企業に科されるわけではありません。
刑罰が定められている解雇は、法律で解雇できない場合として明記している以下の解雇になります。
- 産前産後期間中の解雇(労働基準法19条)
- 業務災害の解雇(労働基準法19条)
- 30日前の予告期間をおくか、30日分の平均賃金を支払うルールに違反した解雇(労働基準法20条)
これらに違反する解雇は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法119条1号)。
また、刑罰は科されないものの、「不当解雇の効果」の項目で解説したとおり、不当解雇となった場合には、会社はそれまでの給与と従業員の復職を余儀なくされてしまいます。
したがって、不当解雇の影響は決して無視できるようなものではありません。
加えて、不当解雇がマスコミなどを通じて社会的に発信されてしまうと、近年話題のブラック企業という印象を与えてしまいかねず、その後の採用活動に悪影響が及んだり、人材の流失の可能性も高まってしまいます。
こうした点からも解雇は慎重に検討して進めなければならないといえます。
不当解雇を撤回したいと思ったらすべきこと
まずは専門家に相談すべき
仮に、会社側が自ら行った解雇について、従業員側から争われ、撤回も視野に入れているという状況であれば、まずは専門家である弁護士に相談すべきでしょう。
安易に解雇を撤回すれば、会社として解雇を通知していた従業員との今後の関係性にも影響を与えますし、そもそも解雇を行った会社の立場と矛盾する行動になります。
撤回の撤回は、当然できないと考えるべきです。
一度冷静になるという観点からも専門家の意見を聞いた上で、これまでの解雇に至る経緯と解雇後の整理を行って、今後の対応を検討していくのが得策でしょう。
不当解雇で訴えられた場合の企業側の対応策

会社側で解雇を行って、その後従業員側から不当解雇で訴えられた場合、どのように対応すべきでしょうか?
以下では、いくつかのポイントを押さえながら解説していきます。
解雇の理由をしっかりと整理する
解雇を会社が行っている以上、従業員を解雇したいと考えた理由があるはずです。
そもそも解雇を通知したのちに従業員側から要求があれば解雇理由を記載した解雇理由証明書を作成して、従業員側に渡さなければなりません。
多くのケースでは、この解雇理由証明書を要求してきます。
その際に、解雇理由を漏れなく、就業規則などの矛盾もなく説明しておかなければなりません。
逆にいえば、そもそも解雇理由証明書で解雇理由が書けないような解雇は不当解雇となる可能性が高いということです。
「あいつが嫌いだったから」といった理由は解雇理由証明書には記載できません。
このように、会社側で解雇を争われた場合には、その以前の段階からも解雇の理由をしっかりと整理しておくことが大切になります。
解雇の理由となっている証拠の確認をする
次に、解雇の理由を整理したら、その理由となっている事実の証拠は何か、どのような証拠なのかを確認しておくことも大切です。
例えば、従業員が会社の商品や現金を盗んだという窃盗や横領の場合、防犯カメラの映像や他の従業員の目撃証言などが証拠になり得ます。
また、遅刻を繰り返す問題社員ということが解雇の理由であれば、遅刻したことの証拠としてタイムカードや注意してきたことを示す指導書や注意書、本人の反省文などが証拠になり得ます。
顧客からの重大なクレームが多数あがった能力不足の社員ということが解雇の理由の場合、顧客からのメールや苦情窓口でのやり取りが証拠になるでしょう。
このように、解雇の理由が整理できると、その理由を裏付ける証拠としてどのようなものがあるのか、従業員側が事実自体を争ってきた場合に対応できる証拠なのかを押さえておくことができます。
専門家に相談する
その上で、従業員側から不当解雇と争われている以上、専門家である弁護士に対応を依頼する必要性は高いといえるでしょう。
弁護士としては、従業員側の訴えている内容や状況を踏まえて、どのように対応するのがよいか検討し、また解雇の理由とそれに関する証拠の有無、証拠の中身を踏まえて、方針を決定します。
主なケースとしては、以下のような段階があります。
示談交渉の場合
従業員個人で不当解雇と争ってくるケースと弁護士を代理人にして争ってくるケースが考えられます。
特に弁護士同士であれば、解雇理由証明書を要求してくるでしょうから、この証明書にどのような事実を記載するのか、それに対して従業員側がどのように主張してくるのかを予想しながら、対応を検討します。
その上で、会社側の意向、解雇が有効と判断される見込み度を考慮しながら、従業員側と示談により解決することができるのか、裁判になる可能性がどの程度あるのか、示談により解決する見込みがあるとして、どのラインを解決ラインに設定するのかを見極めながら交渉を行っていくことになります。
労働組合に加入した場合
会社が従業員を解雇した場合、従業員が労働組合、ユニオンに加入して解雇が不当だと争ってくることがあります。
このとき、会社側としては、すでに解雇した従業員だから労働組合に加入しても無視しておけばよいと考えるかもしれませんが、それはできません。
解雇をした従業員であっても、その解雇に関して労働組合に加入して団体交渉を申し入れてきた場合には、交渉のテーブルにつかなければなりません。
仮に交渉のテーブルにすらつかない場合には、不当労働行為として別の問題に発展してしまいます。
したがって、解雇した従業員が労働組合に加入した場合には、団体交渉の中で会社側の解雇の理由、解雇が正当であることを主張していくことになります。
労働組合としては、解雇された従業員の団体交渉については、かなりヒートアップする可能性が高いため、慎重に対応をしていく必要があります。
労基署を介してきた場合
従業員が労働基準監督署に不当解雇だと相談をした場合、労働基準監督署に所属する労働基準監督官が会社に監督という名目で調査にくることがあります。
労基署が介入してきた場合、仮に解雇に形式面で不備があれば、その点を捉えて是正勧告などの方法で解雇の撤回を労基署として求めてくる可能性が出てきます。
内容面での問題が争われているケースでは、労基署としては双方の言い分を聞きつつ、解決できないかを図るという形での関与になるケースが多いため、弁護士が会社の代理人として、労働基準監督官とのやり取りの窓口になって、話を進めていくという対応をしていきます。
労働審判、裁判の場合
仮に、解雇をした従業員が示談交渉や労働組合を介した上でも解決が図れず、裁判所へ救済を求めて手続を行った場合には、裁判所の対応を行っていくことになります。
この局面になると、まさに解雇が正当なものとして有効なのか、不当なものとして無効になるのかが司法の場に委ねられることになります。
したがって、会社側として解雇に至った経緯、理由について詳細を証拠とともに主張していくことになります。
弁護士としては、どのような主張の組立てをすることが適切なのか、会社側と打ち合わせをしながら、進めていくことになります。
このように、労働審判や裁判まで進むケースでは、裁判対応という日頃の会社の業務とは全く異なる専門的な対応が要求されることになりますので、弁護士の存在は必要不可欠といえるでしょう。
不当解雇を争った裁判例(解雇の無効請求が認められた例・認められなかった例)

以下では、解雇が正当で有効なものか、それとも不当で無効なものかが争われた具体的な裁判例をいくつか紹介して解説をしていきます。
整理解雇
まず、整理解雇についてみていきます。
判例 正当な解雇として有効とされた事例
三陸ハーネス事件(仙台地裁平成17年12月15日決定)
【事案の概要】
18人の正社員が所属しているA社で、生産拠点を海外に移転することに伴って、18人が所属する工場そのものを閉鎖することを決定して、整理解雇をしたという事案。
【裁判所の判断】
裁判所は、生産拠点を海外に動かすという決断自体は唯一の株主であり、唯一の取引先の会社の判断であったとして、海外の3倍ほどのコストとなっている工場を海外に切り替えることは経営戦略上合理的であり、A社の事業自体は営業利益、経常利益ともマイナスとなる状況であったとして人員削減の必要性を認め、かつ、組合との団体交渉を複数回行い、個人面談も実施し、再就職活動のための特別休暇を与えたといったA社の対応も踏まえて整理解雇に至ったという事情から、解雇は正当で有効と結論づけています。
判例 正当な解雇として有効とされた事例
東洋水産川崎工場事件(横浜地裁川崎支部決定平成14年12月27日)
【事案の概要】
工場の老朽化に伴って、別工場への転勤か関連会社へのパートタイムでの雇用と退職金の加算を提案したものの従業員側がこれを拒否したため整理解雇に至ったという事案。
【裁判所の判断】
裁判所は、工場の閉鎖は老朽化が原因でこの経営判断が合理性を欠く不当なものとはいえないとして、人員削減の必要性を認めました。その上で、会社が工場閉鎖を理由にすぐに解雇をすることなく、別工場への転勤や関連会社への異動といった提案をし、解雇を回避する具体的な活動を行った上で、それでも了承しなかった従業員を解雇したという経緯に照らして、整理解雇は有効であると結論づけています。
判例 不当解雇として無効とされた事例
ロイズ・ジャパン事件(東京地裁平成25年9月11日判決)
【事案の概要】
本社から割り当てられた経費削減策を実現させるために、20名の正社員ポストのうち5つを廃止することを決めて、そのうちの1つのポストにいた従業員を解雇した事案。
【裁判所の判断】
裁判所は、解雇に至る前にこの従業員に対して退職勧奨を行っているものの、これを拒否したから解雇という流れについて、20名のポストを5つ削るにあたって、削るポストの従業員にだけ退職勧奨をするのではなく、20名全員に希望退職を募るべきであったとして、解雇を不当なものとして無効と判断しています。
この裁判例では整理解雇4要件のうち、人選の合理性、手続の妥当性の要件が満たされていないと判断されたものといえます。
判例 不当解雇として無効とされた事例
日本通信事件(東京地裁平成24年2月29日判決)
【事案の概要】
4期連続赤字となった会社が増資のために株価を回復する必要性があると判断し、希望退職を募り、その上で応じない人員を整理解雇したという事案。
【裁判所の判断】
裁判所は、4期連続の赤字状態で先ほどのロイズ・ジャパン事件と違って、希望退職も募っているにもかかわらず、解雇を不当と判断しました。
この判断に至った理由としては、従業員に希望退職を募りつつ、社長の役員報酬の1億7000万円という金額を特に変更しないまま、希望退職の際の退職金が100万円に満たないという事実から、解雇を回避する努力がいまだに足りないと考えたからです。
懲戒解雇
判例 正当な解雇として有効とされた事例
炭研精工事件(最高裁平成3年9月19日判決)
【事案の概要】
中卒または高卒の人を対象に募集を行っていた会社に、高卒としてエントリーした者が実際には、大学中退であったこと、採用手続中には刑事裁判を受けている状態であり、入社後に執行猶予判決が下されたことがのちに判明したため、重大な経歴詐称として懲戒解雇された事例。
【裁判所の判断】
裁判所は、雇用関係は、労働者と使用者との相互の信頼関係に基礎をおく継続的な関係であるから、使用者が雇用しようする労働者に対して、必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合には、労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務を負うとして、経歴を偽ったことは、懲戒解雇事由に当たると判断しています。また、雇用された後に執行猶予がついているとはいえ、懲役刑に処せられたことは懲戒解雇事由に該当するともして、解雇は正当と判断しています。
この事例のように、経歴詐称があった場合には、懲戒解雇が有効になることはあります。ただし、経歴詐称があれば全てのケースで懲戒解雇が有効になるわけではなく、重大な経歴詐称に限られています。
判例 不当解雇として無効とされた事例
ネスレ日本事件(最高裁平成18年10月6日判決)
【事案の概要】
大声で怒鳴った上、被害者のネクタイや襟をつかんで身体を壁に押し付けるという暴行を加えたり、複数回にわたって暴力を振るった従業員に対し、事件が起こってから7年経過した段階で懲戒解雇(諭旨解雇)をした事案。
【裁判所の判断】
最高裁は、職場内で起こった暴力事件について7年以上経った時点で行う必要性はなく、暴力の程度などからしても直ちに諭旨退職処分に値する行為とも言い難いとして、不当解雇と結論づけました。
この事案では、会社側は検察官の不起訴処分が出たことを受けて改めて処分を検討することにしたと主張していましたが、最高裁は、「本件各事件は職場で就業時間中に管理職に対して行われた暴行事件であり、被害者である管理職以外にも目撃者が存在していたのであるから、上記の捜査の結果を待たずとも・・・・処分を決めることは十分に可能であった」と判断しています。
普通解雇
普通解雇にはさまざまな理由による解雇が含まれますので、以下では解雇理由に関連して事例を解説していきます。
私傷病を原因とする解雇
判例 正当な解雇として有効とされた事例
カール・ハンセン&サンジャパン事件(東京地裁平成25年10月4日判決)
【事案の概要】
家具の輸入会社で経理担当の従業員がギランバレー症候群という病気で四肢麻痺の症状になったことで解雇された事例。
【裁判所の判断】
裁判所は、解雇に至るまでに四肢麻痺の状態になって1年以上経過し、この段階で会社が解雇予告をしようとした際に従業員からあと5、6か月待って欲しいと要請されたことから、これを受け入れて待ってあげ、待ったけれどもそれほど回復しなかったという医師の診断書を踏まえて解雇は正当なものと判断しています。
判例 不当な解雇として無効とされた事例
K社事件(東京地裁平成17年2月18日判決)
【事案の概要】
資材管理業務をしていた従業員が躁うつ病で欠勤することが増え、出勤しても業務がままならない状態となったため7か月休職期間を設け、その後総務で補助をさせていたが、再度躁うつ病が悪化したため10か月後に解雇した事例。
【裁判所の判断】
裁判所は、かかりつけの医師が躁うつ病の軽躁状態のため通院は必要だが事務作業は可能という診断書を提出していたことやこれを受けて会社の方で専門医にアドバイスを求めたような事情がないこと、再度の休職により改善も可能であったかもしれないとして、この段階で解雇までは不当と結論づけています。
このように私傷病による業務の遂行が困難な事例においては、休職制度が会社にあるかどうか、あるとすれば、その制度を適用させているかどうか、それ以上に会社が配慮をしている事情はあるか、医師の診断内容、会社が医師に相談していたかどうかといった事情が考慮されています。
能力不足
判例 正当な解雇として有効とされた事例
日水コン事件(東京地裁平成15年12月22日判決)
【事案の概要】
建設コンサルティング会社にSEとして中途採用されたものの、システムの納品後にまったくシステムが機能しないというトラブルを起こし、顧客からのクレームだけでなく社内での苦情も重なり、上司にも反抗的な態度を取るに至ったことで解雇された事例
【裁判所の判断】
この事例では、裁判所は、たんに技術・能力・的確性が期待されたレベルに達しないというのではなく、著しく劣っていて職務の遂行に支障が生じており、かつそれは簡単に矯正できないものであったと判断して、解雇を有効としています。
判例 不当な解雇として無効とされた事例
ブルームバーグ・エル・ビー事件(東京高裁平成25年4月24日判決)
【事案の概要】
通信社記者として採用された従業員が会社から能力不足を指摘され、自宅待機を経て解雇された事案。
【裁判所の判断】
裁判所は、入社直後から「期待に満たない」との評価を受け、その後アクションプランやP I P(Performance Improvement Plan)を命じられていたという事実を認定し、「上司・同僚との関係、執筆スピードの遅さ、記事本数の少なさ、記事内容の質の低さのいずれについても、労働契約の継続を期待できない程に重大なものとまでは認められ」ないとして、さらに従業員が改善しようとする意向と態度をP I Pの中などで示しており、解雇は客観的・合理的理由を欠くとして不当と判断されています。
会社にはどうしても、できる社員とできない社員が出てきます。
このときできない社員をどうにかして解雇したいと考える会社や経営者も多くいると思います。
しかしながら、裁判所は単に能力不足、できないという理由ではなかなか解雇を正当なものとして判断してくれないのが実情です。
能力不足を示す具体的なエピソード、それが一定期間継続していること、会社が改善するために面談や教育を尽くしたこと、それでも改善がみられなかったことが証拠により明らかにされなければいけません。
正当な解雇と認められた先ほどの事例でも、SEとして採用されたにも関わらず、システムの一部バグではなく、納品したものがまったく作動しないという重大な欠陥があるものを顧客に出してしまったこと、その後もクレームが多発していたこと、これに対して、改善する意向を示すどころか上司にはむかったというエピソードがあったことが判断に影響していると考えられます。
まとめ
ここまで解説してきたように、会社が行う解雇については、様々な制限が課せられており、要件が厳格になっています。
仮に、こうした要件の検討をないがしろにして解雇を安易に行ってしまうと、不当解雇としてのちのち会社に重大な影響が及んでしまうことになります。
したがって、解雇を検討している段階で早めに専門家である弁護士に相談すべきといえます。
また、従業員側から不当解雇として争われている場合にも、速やかに専門家である弁護士に相談、依頼をしてサポートを受けた上で対応していくべきでしょう。