外国人労働者の法律関係
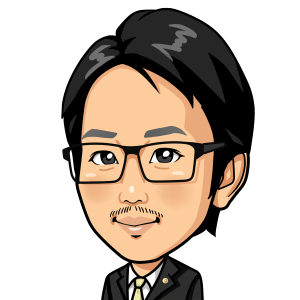 外国人労働者を雇用する場合に、まず押さえておかなければならないのが、外国人労働者との法律関係です。
外国人労働者を雇用する場合に、まず押さえておかなければならないのが、外国人労働者との法律関係です。
具体的には、どの国の法律が適用されるのかという点と紛争が生じた場合にどの国の裁判所が審理を行うかという点です。
前者については、準拠法の問題、後者については裁判管轄の問題です。
こうした準拠法や裁判管轄についての問題は外国人労働者を雇用する場合だけでなく、海外の企業とビジネスを行ったり、外国人と国際結婚(あるいは国際離婚)をしたりする場合などでも同じように問題となり得ます。
準拠法
 まず、前者の準拠法についてですが、国際法上のルールに関して、日本には法の適用に関する通則法という法律があります。
まず、前者の準拠法についてですが、国際法上のルールに関して、日本には法の適用に関する通則法という法律があります。
この法律の7条には、「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と定めています。
つまり、原則として契約当事者が契約時にどの国の法律を適用するかを選択することができるわけです。
したがって、外国企業や外国人との取引を行う場合には、準拠法をどの国にするかを契約書に明記するのが通常です。
他方で、こうした準拠法の選択を当事者が行っていない場合には、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法によることとされています(同法8条)。
以上のルールを前提に、外国人労働者との雇用契約について検討していくと、日本で勤務することを前提に外国人労働者を採用する場合、少なくとも企業としては、日本法を適用したいと考えるのが通常でしょうし、最も密接な関係がある地というのも日本だといえます。
したがって、日本国内における外国人労働者との雇用契約の準拠法は日本法というのが基本です。
先ほど紹介した法の適用に関する通則法でも、労働契約の特例として、当該労働契約において労務を提供すべき地の法が最も密接な関係がある地の法と推定する旨の規定が設けられています(12条3項)。
外国人労働者を日本で採用する場合には、日本法が適用されるというのは、企業からしてみれば当たり前だと思うかもしれません。
しかしながら、このことは非常に重要な意味をもちます。
 すなわち、日本人の労働者との間で適用される、民法はもちろん、労働条件の最低基準を定めた労働基準法や企業の従業員に対する安全管理などを定めた労働安全衛生法、雇止めや解雇の条件を定める労働契約法といった各種労働法令が外国人労働者にも適用されるということです。
すなわち、日本人の労働者との間で適用される、民法はもちろん、労働条件の最低基準を定めた労働基準法や企業の従業員に対する安全管理などを定めた労働安全衛生法、雇止めや解雇の条件を定める労働契約法といった各種労働法令が外国人労働者にも適用されるということです。
「外国人だから労働条件を通知しなくても大丈夫」、「外国人だから解雇は自由」、「労災が発生しても外国人は補償の対象としなくてよい」というようなことは全て誤りです。
労働条件を通知しなければ、労働基準法15条違反となりますし、解雇の要件を満たしていなければ労働契約法16条違反となります。
労災が発生した場合には、労災保険の適用がありますし、企業は安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を外国人労働者に対して負わなければなりません。
さらに、最低賃金法も外国人労働者には適用されます。
したがって、外国人労働者を時給500円で雇用するというのは最低賃金法に違反するため違法となります。
実際のケース
2018年秋の入管法改正に際して、国会では技能実習生のデータ改ざんが問題となりました。
このとき、反対する野党は、失踪してしまった技能実習生の中には、最低賃金法に違反する低賃金で過酷な長時間労働を余儀無くされていたという実態を問題視していましたが、これはもちろん合法な取扱いではありません。
労働者の労働条件や労働環境について監督する機関である労働基準監督署は、外国人労働者の増加を踏まえて、外国人労働者の労働条件が遵守されているかどうかを重点事項に据えています。
なお、海外で現地法人を立ち上げるために、外国人労働者を日本で当初採用し、一定の研修を経た上で、海外で勤務してもらう場合、雇用当初は日本の労働法令が適用されることになりますが、その後海外で勤務してもらうことになる段階で現地の労働法が適用されることになる可能性があります。労務提供の地が日本国内ではなくなるためです。
こうしたケースでは、企業は、再度雇用契約書の内容を見直した上で契約書を作成し直すなどして、注意して労務管理をしなければなりません。
裁判管轄
 次に、外国人労働者と万が一、紛争が生じた場合にどこの国の裁判所が審理を行うことができるかという点に関する問題である裁判管轄についてみていきます。
次に、外国人労働者と万が一、紛争が生じた場合にどこの国の裁判所が審理を行うことができるかという点に関する問題である裁判管轄についてみていきます。
ここでは、外国人労働者から企業を訴えるという局面と企業から外国人労働者を訴える局面とが考えられます。
まず、外国人労働者から企業を訴える場合ですが、被告となる企業が日本に事業所を設けているのが通常ですので、事業所の住所地を管轄する日本の裁判所に裁判管轄が認められます(民事訴訟法3条の2第3項)。
また、労働契約に関する労働者側から提起する裁判については、労務の提供の地に裁判管轄が認められているため(民事訴訟法3条の4第2項)、いずれにしても日本の裁判所が裁判管轄を有しています。
他方、企業の方から外国人労働者を訴える場合、当該外国人労働者が訴え提起時に日本国内に居住していれば、問題なく日本の裁判所に管轄が認められます。
被告の住所地が普通裁判管轄として認められているためです(民事訴訟法3条の2第1項、4条)。
しかしながら、外国人労働者が母国に帰国している場合には、この普通裁判管轄が生じないため、検討が必要です。
例えば、外国人労働者に契約違反があったことを理由として損害賠償請求をする場合には、義務履行地としての管轄(民事訴訟法3条の3第1号)、横領などの不法行為があったことを理由として損害賠償請求をする場合には、不法行為地としての管轄(同8号)として日本の裁判所に裁判管轄が認められます。
このように、法的構成によって、日本の裁判所に管轄が認められないかを考えていくことになります。
法的構成に関わらず日本の裁判所で管轄を発生させるためには、雇用契約の段階で合意管轄を事業所の所在地を管轄する裁判所として外国人労働者とする旨を取り交わしておくことも検討すべきでしょう。
対策
 裁判の管轄が日本に認められるからといっても、海外に帰国した外国人労働者を相手に裁判をするのは、裁判書類の郵送(送達)にも手間がかかりますし、実際に損害賠償しても、賠償金を得られるのかという問題が残りますので、企業が外国人労働者に何らかの請求を行う場合には、早めに対策をとることが重要です。
裁判の管轄が日本に認められるからといっても、海外に帰国した外国人労働者を相手に裁判をするのは、裁判書類の郵送(送達)にも手間がかかりますし、実際に損害賠償しても、賠償金を得られるのかという問題が残りますので、企業が外国人労働者に何らかの請求を行う場合には、早めに対策をとることが重要です。
具体的には、退職の前の段階で通知書を送付したり、給料から損害額を天引きするといった方法です。
もっとも、天引きには労働者の同意が必要なため、安易に進めるとトラブルに発展してしまいます。
外国人の労務問題で困った場合には、早めに専門家である弁護士に相談しておくことが寛容です。

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士
所属 / 福岡県弁護士会
保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者
専門領域 / 法人分野:労務問題、外国人雇用トラブル、景品表示法問題 注力業種:小売業関連 個人分野:交通事故問題
実績紹介 / 福岡県屈指の弁護士数を誇るデイライト法律事務所のパートナー弁護士であり、北九州オフィスの所長を務める。労働問題を中心に、多くの企業の顧問弁護士としてビジネスのサポートを行っている。労働問題以外には、商標や景表法をめぐる問題や顧客のクレーム対応に積極的に取り組んでいる。







